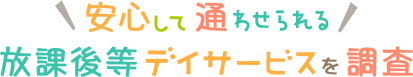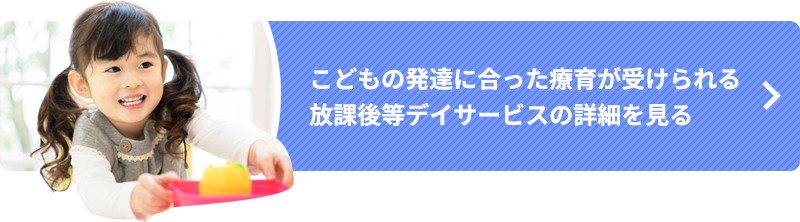発達障害の「パステルゾーン(グレーゾーン)」
 発達障害の「パステルゾーン(グレーゾーン)」は、発達障害の特性が見られるが、診断がつくための基準には達していない状態を指します。医学的な診断名ではなく、あくまでも通称になります。
発達障害の「パステルゾーン(グレーゾーン)」は、発達障害の特性が見られるが、診断がつくための基準には達していない状態を指します。医学的な診断名ではなく、あくまでも通称になります。
診断がつく基準に達していないという状態ですが、抱える問題や症状が軽いという訳ではありません。パステルゾーン(グレーゾーン)ならではの悩みが存在するのは確かです。
このページでは、発達障害のパステルゾーン(グレーゾーン)について解説していきます。
発達障害の「パステルゾーン(グレーゾーン)」とは
発達障害におけるパステルゾーン(グレーゾーン)には、明確な定義は存在しません。知的障害などを判定する基準(DSM-5)には「保育や教育の場で不適応行動が見られるものの、診断がつかないあるいは未受診の子ども」と記されています。
具体的には、医学的な診断基準を全て満たしてはいないけれどいくつかの発達障害の特性を持ち、日常生活を送るうえで困難を抱えている、という定型発達と発達障害の間の境界領域を指す俗称が「パステルゾーン(グレーゾーン)」なのです。
幼少期にパステルゾーン(グレーゾーン)と言われたが、その後年齢を重ね困りごとが増えたり特性が顕著になってきて改めて発達障害の診断名がつくケースも見られます。それでも発達障害の診断がつかず、「軽度、傾向が見られます。」といったあいまいなところでパステルゾーン(グレーゾーン)のままのケースもあります。
はっきりとした診断がつかないので、精神障害者保健福祉手帳や療育手帳の交付はなく、福祉や教育の支援の対象にはなりませんが、パステルゾーン(グレーゾーン)ならではの悩みや問題ごとがあります。こういった手帳の交付がなくても受けることのできる公的支援の利用をすること、学校や職場での周りの方々への理解や協力をお願いすることなどで生活のしやすい環境を作っていくことが大切になってきます。
発達障害パステルゾーン(グレーゾーン)の特徴と症状
発達障害のパステルゾーン(グレーゾーン)によく見られる特徴や症状にはどのようなものがあるのでしょうか。一人一人違った症状が出ることや、どんな環境・場面で症状が強く出るかも異なるといったことがありますが、多く見られる特徴や症状について解説していきます。
特徴と症状
主な発達障害では下に記したような特徴が見られますが、パステルゾーン(グレーゾーン)の症状は、これという特有の特徴や症状は決まっていません。どの発達障害の傾向を持ち合わせているかによって、診断基準を満たさないまでも特徴や症状の一部が見られます。
主な発達障害の特徴と症状
- ASD (自閉症スペクトラム):社会的な交流が苦手。空気読めず、コミュニケーション・対人関係が困難。偏りと強いこだわりを持つ。
- ADHD(注意欠如多動障害):好きなこと以外に集中できず落ち着かない多動性、極端な忘れ物など年齢に見合わない不注意さがあり、思いついたら考えずに衝動的に行動してしまう。
- LD (学習障害):知的な発達に遅れはないが、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算・推論する」の何かひとつが著しく困難で苦手。
パステルゾーン(グレーゾーン)では、上記のような発達障害の傾向がある、という表現で説明を受けることがあります。だからと言って特定の症状が強く出るという訳ではありません。それぞれの持つ特性の程度や現れ方は、体調や環境などによって左右されるという特徴があります。例えば、家で落ち着いた環境にいると症状は弱く、学校では症状が強く出てしまうケースなどはよく見られます。
発達障害パステルゾーン(グレーゾーン)の具体的な症状の事例
- 癇癪がひどく、友達とのトラブルが多い
- 友達に、自分の興味のある話を延々としてしまい相手の話は聞かないので、だんだん距離ができていってしまう
- できないわけではないが、何度も繰り返す漢字の書き取りを授業中に集中してやることができない
- やる気がしなくて授業に集中しなかったり、思ったことをどんどん発言してしまって授業が進まなくなってしまう
- 文字を素早く書くのが苦手で、ノートをとることに時間がかかり授業の内容が頭に入ってこない
子供を伸ばす接し方
多くの親や子育てに関わる大人は、子供が良いことをしたら褒め、間違った時にはしかり、時には諭すことが普通の子育てだと認識しています。しかし、発達障害のパステルゾーン(グレーゾーン)の子供の子育てはなかなかうまくいかず、気が付くと朝から晩まで怒ってばかり…同じことを何度注意してもまた繰り返してしまう…と悩んでいる方も多いのが現状です。
発達障害のパステルゾーン(グレーゾーン)の子供の子育てにはいくつかポイントがあるようです。パステルゾーン(グレーゾーン)であることを個性ととらえ、伸ばしていくには、「個性を理解すること」と「環境を整える事」が重要になってきます。では具体的にどのようなことなのか、ご紹介していきましょう。
個性を理解すること
まずは、一人一人の子供の特徴や個性を具体的に考えてみましょう。ネガティブなことはいつも気になっていることが多く、スラスラでてくるかもしれませんが、良いことも見つけてみてください。その他、良い悪いではないけれど、他の子とは違うなと感じることや好き嫌い、集中して取り組むことなどもできるだけ具体的に沢山挙げていってみてください。
周りの大人がまずその子の個性を理解し、どういったことで日常生活や集団生活で困っているのかを分析し、解決策を考えてあげることが必要になってきます。
環境を整える事
具体的に個性を挙げられたら、次に分析をしてみます。まずは日常の困っていることから。例えば、Aちゃんのケースの場合。何度同じことを注意しても繰り返してしまい、話をちゃんと聞いていないからだと怒られます。話は聞いていますし、言葉は理解できていて、注意した時は正すことができる。なのに「なぜ?」なのかを考えてみました。
Aちゃんは、道路標識が好きで沢山覚えていて、交通ルールはしっかりと守ります。「あぶないから」と注意されたことは耳からだと抜けていってしまいますが、「とまれ」の標識があると止まります。耳よりも目から情報が多く入るタイプなのではないかと分析し、日常生活で注意すべきことはイラストや簡単な言葉で貼ってみることにしました。すると失敗を繰り返す頻度がぐっと減り、お互いのストレスも軽減できたそうです。
このような日常の環境を整えてあげることで解決するケースもあれば、集団生活が苦手で、授業を教室で集中して受けることができずに立ち歩いてしまう、といったケースもあります。
ひと言で環境を変えると言っても、すぐにできることとできない事はありますが、具体的に分析していくことで、無理にできないことを強いるのではなく個性を伸ばしながら解決策を導いていくことができます。周りにいる大人が特性や個性を正しく理解してあげることがまず一番に大切なことなのです。
学童保育や塾を選ぶポイント
ここでは学童保育や塾選びのポイントについてご紹介していきます。
環境が合っているか
通おうとしている学童や塾は、環境が合っているかどうかを確認するようにしましょう。リサーチは大切です。体を動かすのが好きな子なら運動するスペースが十分にあるかどうか、騒々しいのが苦手な子なら利用人数の確認など子供の特性に合わせてチェックポイントをしっかり見ていきます。見学に行ってみて確認するのが良いでしょう。
受入れ実績とサポート体制
同じようなタイプの子を受け入れた実績があるのかどうかなど、実際に先生に問い合わせをしてみましょう。どういったトラブルがあったときにどのようなサポートを行ったのかなど、積極的に聞いてみることが大切です。
このサイトでは、お子さまの発達具合がわかるWISC検査について解説しています。その結果を療育に活かしているおすすめの放課後等デイサービスも紹介しています。
お子さまの発達にあった療育を受けさせたいと思っている方は、ぜひ参考にしてください。
お子さまの発達がわかるWISC検査と
結果を活かす放課後等デイサービスをみる
子どもの特性が分かる発達テスト、WISC検査について解説
 お子さんの受けられる発達検査のひとつにWISC検査があります。その子の持つ特性や発達の凹凸など詳しく数値として分かるのでおすすめです。5歳~16歳11か月の検査では、「言語理解」「知覚推理」「作業記憶」「処理速度」の4項目を調べます。結果をもとに指導に反映してくれる放課後等デイサービスもありますよ。さらに詳しく検査についてまとめたページがありますのでぜひご覧ください。
お子さんの受けられる発達検査のひとつにWISC検査があります。その子の持つ特性や発達の凹凸など詳しく数値として分かるのでおすすめです。5歳~16歳11か月の検査では、「言語理解」「知覚推理」「作業記憶」「処理速度」の4項目を調べます。結果をもとに指導に反映してくれる放課後等デイサービスもありますよ。さらに詳しく検査についてまとめたページがありますのでぜひご覧ください。
- 発達障がいの子どもに通わせたい放課後等デイサービス施設
- あすなろクラブ矢作
- わくわくセブン
- ルアナランド
- Olinace八千代
- 放課後等デイサービス HERO
- 放課後等デイサービス 笑顔(ニコニコ)
- 放課後等デイサービス ぽの
- はばたき
- アースウェル
- 放課後等デイサービス そら
- 放課後等デイサービス まつどっ子
- ウィズ・ユー
- 運動療育こどもプラス新松戸教室
- 放課後等デイサービス みらい
- 放課後等デイサービス ありす
- わくわくクラブ
- LITALICO(りたりこ)
- STEP
- こぱんはうすさくら
- スマートキッズ
- ハッピーテラス
- わいわいプラス
- すきっぷ
- キッズフロンティア
- BRIDGE(ブリッジ)
- ノビルキッズ
- サンタクロース・Jr・もみの木
- かがやきのまち
- 放課後等デイサービス 学び舎
- わくわくbloom
- にじ(AIAI PLUS今井)
- アフタースクールセンター・ウェル
- わくわくぎふと鎌取
- 放課後等デイサービスまりも
- わくわくすまいる
- スマイルファクトリー
- ハビープラス
- 輝HIKARIさいたま
- ドリームボックス
- 放課後等デイサービス夢門塾
- 運動学習支援教室うめっこ本庄
- はつらつ入間教室
- はなまるキッズ
- Gripキッズ
- にこにこクラブ
- こすもすカレッジ
- 放課後等デイサービスとは?基礎知識を紹介
- 中高校生向けの放課後等デイサービスでは
どんな内容が受けられる? - 放課後等デイサービスのイベントについて
- 放課後等デイサービスの2類型化とは?
- 放課後等デイサービスにおける連絡帳の役割とは?
- 放課後等デイサービスを掛け持ちしてもいい?
- 放課後等デイサービスはいつまで通わせるとよいのか?
- 不登校の子どもは放課後等デイサービスを利用できる?
- 放課後等デイサービスの集団療育と個別療育はどちらを選ぶべき?
- 放課後等デイサービスの運動療育とは
- 放課後等デイサービスと学童の違いについて
- 放課後等デイサービスの活動内容について
- 対象となるお子さん
- 利用方法
- 受給者証の取得方法
- 料金
- 選び方
- 送迎
- 放課後等デイサービスの一日の流れ
- 事業所を変更する際の変更届について
- 発達障がいの知能検査
- 発達障害の子どもを持つ方の子育ての悩み
- 発達障がいを持つ中学生の困りごととは?
- 発達障害と癇癪(かんしゃく)との関係とは
- 発達障害の子どもの偏食・好き嫌いとその対策
- 発達障害児のお子さんの片付けをサポートするには?
- 着替えが苦手な発達障害児のサポート
- 発達障害のお子さんのお風呂の入れ方
- 発達障害のお子さんへの叱り方は?接し方で反応は変わる!
- 発達障害の我が子が勉強しない理由は?障害に合わせた対策
- 子どもが寝ないのはなぜ?発達障害と睡眠障害の関係について
- 発達障害で落ち着きのない子どもへの対応
- 言うことを聞かない発達障害の子どもへの伝え方は?
- 発達障害の子どもは感覚刺激への偏りが生じる
- 発達障害の子どもが迷子になりやすい理由と対策
- ものをなくすのは発達障害の特性?理由と対策を紹介
- 発達障害で怒りをコントロールできない子どもへの対応
- 友達づきあいが苦手な発達障害の子ども。
その理由と対応法 - 発達障害児は運動が苦手?
特性とケアの方法について