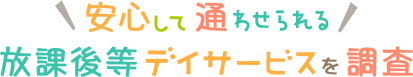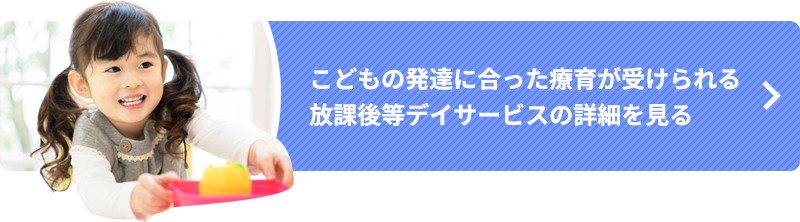受給者証の取得方法
このページでは、放課後等デイサービスを受けるために必要な受給者証の取得方法と、受給者証を取得することでどのようなサービスを受けられるかについて解説していきます。
放課後等デイサービスの受給者証とは

障害者児童を持つ家庭は自治体から二種類の受給者証を発行してもらうことが可能です。一つは医療サービスなどを受けるための受給者証。そして、もう一つが放課後等デイサービスの費用を始めとした福祉サービスを受ける際に手当が支給される受給者証となります。
放課後等デイサービスなどの通所施設に通わせる際に手当を支給してもらえる「通所支援」の他に、施設にお子様を預ける際に手当を支給される「入所支援」のための受給者証も存在しています。
また、受給者証には発行する前に施設や役所の方と相談・ヒアリングして決定した、お子様が月に通所する回数・保護者氏名・生年月日・サービスの種類などが記載されています。
療育手帳との違い
障害者児童に支給される愛の手帳やみどりの手帳を始めとする療育手帳との違いは、療育手帳が障害名や程度を証明するために都道府県が発行している一方で、受給者証は福祉や医療といったサービスを利用するための証明として市町村が発行している点にあります。また、療育手帳だけで放課後等デイサービスを利用しようとすると、全額自己負担になってしまう点にも注意が必要です。放課後等デイサービスの利用を検討している方は、療育手帳を所持済みでも必ず受有者証を取得しておいてください。
ちなみに、療育手帳が取れなかった方でも受給者証を申請することは可能です。
受給者証を持つことのメリット
では、受給者証で果たしてどのような支援を受けることができるのでしょうか。こちらでは、受給者証でどんなサービスを受けられるかについて解説していきます。
障害児施設への通所・入所が可能となる

基本的に放課後等デイサービスをはじめとした障害児通所施設や障害児入所施設の利用には、療育手帳か受給者証が必須となります。なので、療育手帳をお持ちでない且つお子様を通所施設に通わせたいと考えている方であれば、まずはこちらの受給者証の取得しておく必要があるのです。
ただし、受給者証があれば通所施設に入り放題というわけではなく、受給者証に書かれた日数分しか利用することはできません。例えば、支給量が「20日/月」と書かれている受給者証であれば、月に最大で20日までなら通所施設を利用できます。
障害児施設の利用料金を支援してもらえる
放課後等デイサービスには当然利用料金がかかります。しかし、受給者証があれば、その費用の9割を自治体に負担してもらえるので、限りなく家計への負担を抑えることが出来ます。
受給者証の手続きについて
放課後等デイサービスの受給者証を受けとるまでのステップは大きく5つに分けられます。そちらを分かり易くまとめたので、参考にしてください。
利用相談
まずは市区町村の窓口に相談してください。通所支援と入所支援の窓口は別々にあるので、混同しないように注意しましょう。通所支援は「福祉相談窓口・障害児相談支援事業所」になります。担当者に、事前に電話などでアポイントメントをとりつけておくとスムーズに運ぶことが出来るでしょう。
利用相談では最初に子供の状況を聞かれることが多いので、母子手帳を持参することをおすすめします。過去に医者に対して相談した内容や発達検査の受検歴などを覚えていれば、その内容や結果を伝えましょう。
窓口では地域の事業所について情報を提供してくれることも。もしも既に利用した施設が決まっている場合や、施設に対して求める具体的なイメージが固まっているのであれば、それも伝えておくと良いでしょう。受給者証の申請に必要な書類が市区町村によって差異があることもあるので、それもこの際に忘れずに聞いておきましょう。
施設見学
次に実際に利用したいと考えている事業所に見学に行ってみましょう。既にお子様を通わせたいと考えている施設が決まっている場合は、こちらはスキップして頂いても大丈夫です。
まず見学に行ったら、利用についての具体的な相談をすることを心がけましょう。事前に聞きたいことは手帳などにメモしておくと、スムーズに質問することができます。場合によっては事業所で利用計画案を作成してくれることも。また、地域によって受給申請に必要な書類の中に「事業所の意見書」が含まれているので、この際忘れずに作成してもらいましょう。
目的のサービスが決まったら、申請に必要な障害児支援利用計画案を作ります。障害児支援利用計画案は、障害のある児童への効果的な支援を継続する際、事業者と円滑な連携を行うために作成するものです。こちらは施設の方が作る場合もあれば、セルフプラントとして家族や支援者が作成することもできます。
申請書等の提出
以上のことを済ませたら、受給者証を取得するために障害児通所給付費支給の申請を行いましょう。障害児通所給付費支給の申請先は、市町区村の福祉担当窓口になります。
基本的に必要な書類は、「障害児通所給付費支給申請書」「障害児支援利用計画案」「所得などを証明する書類」「発達に支援が必要なことがわかる書類(児童相談所・市町村保健センター・医療機関などの意見書や療育手帳や意見書など)、被保険者証、医師の療育意見書(※医療型自動発達支援の場合のみ)、マイナンバーなど。
繰り返しになりますが、市町区村次第で必要な申請書類は違うので、必ず事前に必要な書類の種類を窓口で聞いておくようにしましょう。
調査と審査
申請を済ませたら、次は支給の有無やサービス内容を決定するための聞き取り調査(ヒアリング)を受けてください。ヒアリングでは、障害の種類や程度などを尋ね、お子様が要件を満たしているかどうか、そしてお子様に対して適切なサービスの量や内容についての検討も同時に行われます。
ヒアリングは、面接調査や訪問調査を実施することもあります。その際には、状況の聞き取りやサービスを利用する意向についての聴き取りなどが行われる場合もあります。審査はヒアリング終了後に行われ、給付が決定するのはおよそ1月半から2月かかることもあるようです。
通所受給者証の交付
無事審査を通過すると、「通所受給者証」が交付されます。受給者証には、ヒアリングや面談を通して決定された、お子様が受けることの可能なサービスの内容や量が記載されています。自身の希望がどれほど通ったのか、どれほど支援してもらえるか忘れず確認しておきましょう。
交付を受けたら、障害児支援利用計画を作成しましょう。相談支援事業所が受給者証の給付決定内容に基づいて、利用を希望する事業者と連絡して調整・作成してくれます。
ここまで終わらせれば、あとはどの施設にお子様を預けるか決めるだけです。
このサイトでは、お子さまの発達具合がわかるWISC検査について解説しています。その結果を療育に活かしているおすすめの放課後等デイサービスも紹介しています。
お子さまの発達にあった療育を受けさせたいと思っている方は、ぜひ参考にしてください。
お子さまの発達がわかるWISC検査と
結果を活かす放課後等デイサービスをみる
子どもの特性が分かる発達テスト、WISC検査について解説
 お子さんの受けられる発達検査のひとつにWISC検査があります。その子の持つ特性や発達の凹凸など詳しく数値として分かるのでおすすめです。5歳~16歳11か月の検査では、「言語理解」「知覚推理」「作業記憶」「処理速度」の4項目を調べます。結果をもとに指導に反映してくれる放課後等デイサービスもありますよ。さらに詳しく検査についてまとめたページがありますのでぜひご覧ください。
お子さんの受けられる発達検査のひとつにWISC検査があります。その子の持つ特性や発達の凹凸など詳しく数値として分かるのでおすすめです。5歳~16歳11か月の検査では、「言語理解」「知覚推理」「作業記憶」「処理速度」の4項目を調べます。結果をもとに指導に反映してくれる放課後等デイサービスもありますよ。さらに詳しく検査についてまとめたページがありますのでぜひご覧ください。
- 発達障がいの子どもに通わせたい放課後等デイサービス施設
- あすなろクラブ矢作
- わくわくセブン
- ルアナランド
- Olinace八千代
- 放課後等デイサービス HERO
- 放課後等デイサービス 笑顔(ニコニコ)
- 放課後等デイサービス ぽの
- はばたき
- アースウェル
- 放課後等デイサービス そら
- 放課後等デイサービス まつどっ子
- ウィズ・ユー
- 運動療育こどもプラス新松戸教室
- 放課後等デイサービス みらい
- 放課後等デイサービス ありす
- わくわくクラブ
- LITALICO(りたりこ)
- STEP
- こぱんはうすさくら
- スマートキッズ
- ハッピーテラス
- わいわいプラス
- すきっぷ
- キッズフロンティア
- BRIDGE(ブリッジ)
- ノビルキッズ
- サンタクロース・Jr・もみの木
- かがやきのまち
- 放課後等デイサービス 学び舎
- わくわくbloom
- にじ(AIAI PLUS今井)
- アフタースクールセンター・ウェル
- わくわくぎふと鎌取
- 放課後等デイサービスまりも
- わくわくすまいる
- スマイルファクトリー
- ハビープラス
- 輝HIKARIさいたま
- ドリームボックス
- 放課後等デイサービス夢門塾
- 運動学習支援教室うめっこ本庄
- はつらつ入間教室
- はなまるキッズ
- Gripキッズ
- にこにこクラブ
- こすもすカレッジ
- 放課後等デイサービスとは?基礎知識を紹介
- 中高校生向けの放課後等デイサービスでは
どんな内容が受けられる? - 放課後等デイサービスのイベントについて
- 放課後等デイサービスの2類型化とは?
- 放課後等デイサービスにおける連絡帳の役割とは?
- 放課後等デイサービスを掛け持ちしてもいい?
- 放課後等デイサービスはいつまで通わせるとよいのか?
- 不登校の子どもは放課後等デイサービスを利用できる?
- 放課後等デイサービスの集団療育と個別療育はどちらを選ぶべき?
- 放課後等デイサービスの運動療育とは
- 放課後等デイサービスと学童の違いについて
- 放課後等デイサービスの活動内容について
- 対象となるお子さん
- 利用方法
- 受給者証の取得方法
- 料金
- 選び方
- 送迎
- 放課後等デイサービスの一日の流れ
- 事業所を変更する際の変更届について
- 発達障がいの知能検査
- 発達障害の子どもを持つ方の子育ての悩み
- 小学1年生の発達障害の特徴・困り事は?
- 発達障がいを持つ中学生の困りごととは?
- 発達障害と癇癪(かんしゃく)との関係とは
- 発達障害の子どもの偏食・好き嫌いとその対策
- 発達障害児のお子さんの片付けをサポートするには?
- 着替えが苦手な発達障害児のサポート
- 発達障害のお子さんのお風呂の入れ方
- 発達障害のお子さんへの叱り方は?接し方で反応は変わる!
- 発達障害の我が子が勉強しない理由は?障害に合わせた対策
- 発達障害の子供が「寝ない」理由とは?家庭でできる対策と支援サービス
- 発達障害で落ち着きのない子どもへの対応
- 言うことを聞かない発達障害の子どもへの伝え方は?
- 発達障害の子どもは感覚刺激への偏りが生じる
- 発達障害の子どもが迷子になりやすい理由と対策
- ものをなくすのは発達障害の特性?理由と対策を紹介
- 発達障害で怒りをコントロールできない子どもへの対応
- 友達づきあいが苦手な発達障害の子ども。
その理由と対応法 - 発達障害児は運動が苦手?
特性とケアの方法について