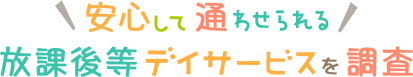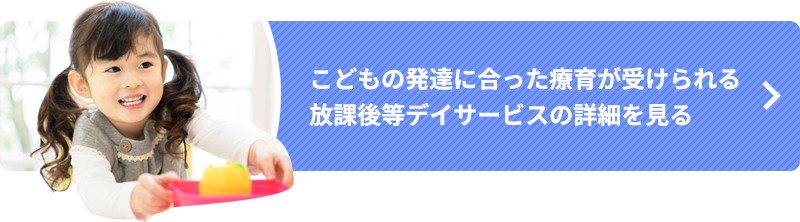発達障害で落ち着きのない子どもへの対応
このページでは、発達障害で落ち着きがない子どもへの対応や間違った接し方、体験談などを紹介しています。
発達障害で落ち着きがない子どもには集中できる環境を整える
発達障害の中でも注意欠陥多動性障害(ADHD)の症状のある子どもは、集中力が続かず落ち着きがないのが特徴です。同じところでじっとできず、授業中に歩き回ったり、他の人が話しているのを遮って話し始めたりしてしまいます。
このような問題行動は子どもが落ち着きをなくしてしまう要因を取り除くことで、ある程度抑制できます。つまり子どもが集中できる環境を整えてあげる必要があるのです。
発達障害の子どもは授業中であっても、気になるものが目に飛び込んでくると集中力を失ってしまいがちです。他の人が視界に入りにくい一番前の席に変えてもらう、教室の前方には掲示物を貼らないなどの対応をしてもらいましょう。
また、周囲と一緒に行動するのが苦手な子どもの場合には、「イスに座る」「静かに話を聞く」などの文字やシンプルなイラストを使って子どもの理解をサポートしてあげるのも有効です。
発達障害で落ち着きがない子どもを叱るのは逆効果
発達障害の子どもの多動症状は意図的なものではありません。不安な気持ちを解消しようとして、うろうろしたり、いろいろなところに触れたりしています。授業を邪魔しよう、親を困らせようとして落ち着きがない行動を取っているわけではないので、怒鳴って叱りつけると逆効果です。
発達障害の子どもを大きな声で叱りつけたり、脅すように怒鳴ったりすると不安な気持ちになってパニックを起こしてしまいます。焦りやいらだちから自己コントロールができなくなって、泣きわめき癇癪を起こすこともあるのです。
落ち着きがない発達障害の子どもを注意するときには、子どもに近づいて目を見ながら、落ち着きのある声で注意してください。このときに、「なぜおとなしく座らないといけないのか」などの理由も併せて伝えてあげるのがよいでしょう。
発達障害で落ち着きがない子どもを持つ保護者の体験談
3人の子どものうち2人に発達障害があります。子どもが小さい頃はあまりにも大変で、少し目を離したうちに視界から消えているようなことが頻繁に起こっていました。家の中でもちょっとしたことで泣きじゃくり、突発的に脱走してしまうので、1日中子どもから目が話せません。ママ友に相談すると励ましの言葉を受けましたが、逆に心配になってしまったこともあります。
落ち着きがない発達障害の子どもには環境を整えてあげることが大事
発達障害の症状で子どもの落ち着きがないことに困っている方は多いでしょう。子どもが集中力を失わないように環境を整えてあげることで、自分をコントロールしやすくなります。放課後等デイサービスを利用して、子どもの自主性を伸ばしてあげるのことも自己コントロールの向上につながります。
このサイトでは、お子さまの発達具合がわかるWISC検査について解説しています。その結果を療育に活かしているおすすめの放課後等デイサービスも紹介しています。
お子さまの発達にあった療育を受けさせたいと思っている方は、ぜひ参考にしてください。
お子さまの発達がわかるWISC検査と
結果を活かす放課後等デイサービスをみる
子どもの特性が分かる発達テスト、WISC検査について解説
 お子さんの受けられる発達検査のひとつにWISC検査があります。その子の持つ特性や発達の凹凸など詳しく数値として分かるのでおすすめです。5歳~16歳11か月の検査では、「言語理解」「知覚推理」「作業記憶」「処理速度」の4項目を調べます。結果をもとに指導に反映してくれる放課後等デイサービスもありますよ。さらに詳しく検査についてまとめたページがありますのでぜひご覧ください。
お子さんの受けられる発達検査のひとつにWISC検査があります。その子の持つ特性や発達の凹凸など詳しく数値として分かるのでおすすめです。5歳~16歳11か月の検査では、「言語理解」「知覚推理」「作業記憶」「処理速度」の4項目を調べます。結果をもとに指導に反映してくれる放課後等デイサービスもありますよ。さらに詳しく検査についてまとめたページがありますのでぜひご覧ください。
- 発達障がいの子どもに通わせたい放課後等デイサービス施設
- あすなろクラブ矢作
- わくわくセブン
- ルアナランド
- Olinace八千代
- 放課後等デイサービス HERO
- 放課後等デイサービス 笑顔(ニコニコ)
- 放課後等デイサービス ぽの
- はばたき
- アースウェル
- 放課後等デイサービス そら
- 放課後等デイサービス まつどっ子
- ウィズ・ユー
- 運動療育こどもプラス新松戸教室
- 放課後等デイサービス みらい
- 放課後等デイサービス ありす
- わくわくクラブ
- LITALICO(りたりこ)
- STEP
- こぱんはうすさくら
- スマートキッズ
- ハッピーテラス
- わいわいプラス
- すきっぷ
- キッズフロンティア
- BRIDGE(ブリッジ)
- ノビルキッズ
- サンタクロース・Jr・もみの木
- かがやきのまち
- 放課後等デイサービス 学び舎
- わくわくbloom
- にじ(AIAI PLUS今井)
- アフタースクールセンター・ウェル
- わくわくぎふと鎌取
- 放課後等デイサービスまりも
- わくわくすまいる
- スマイルファクトリー
- ハビープラス
- 輝HIKARIさいたま
- ドリームボックス
- 放課後等デイサービス夢門塾
- 運動学習支援教室うめっこ本庄
- はつらつ入間教室
- はなまるキッズ
- Gripキッズ
- にこにこクラブ
- こすもすカレッジ
- 放課後等デイサービスとは?基礎知識を紹介
- 中高校生向けの放課後等デイサービスでは
どんな内容が受けられる? - 放課後等デイサービスのイベントについて
- 放課後等デイサービスの2類型化とは?
- 放課後等デイサービスにおける連絡帳の役割とは?
- 放課後等デイサービスを掛け持ちしてもいい?
- 放課後等デイサービスはいつまで通わせるとよいのか?
- 不登校の子どもは放課後等デイサービスを利用できる?
- 放課後等デイサービスの集団療育と個別療育はどちらを選ぶべき?
- 放課後等デイサービスの運動療育とは
- 放課後等デイサービスと学童の違いについて
- 放課後等デイサービスの活動内容について
- 対象となるお子さん
- 利用方法
- 受給者証の取得方法
- 料金
- 選び方
- 送迎
- 放課後等デイサービスの一日の流れ
- 事業所を変更する際の変更届について
- 発達障がいの知能検査
- 発達障害の子どもを持つ方の子育ての悩み
- 発達障がいを持つ中学生の困りごととは?
- 発達障害と癇癪(かんしゃく)との関係とは
- 発達障害の子どもの偏食・好き嫌いとその対策
- 発達障害児のお子さんの片付けをサポートするには?
- 着替えが苦手な発達障害児のサポート
- 発達障害のお子さんのお風呂の入れ方
- 発達障害のお子さんへの叱り方は?接し方で反応は変わる!
- 発達障害の我が子が勉強しない理由は?障害に合わせた対策
- 子どもが寝ないのはなぜ?発達障害と睡眠障害の関係について
- 発達障害で落ち着きのない子どもへの対応
- 言うことを聞かない発達障害の子どもへの伝え方は?
- 発達障害の子どもは感覚刺激への偏りが生じる
- 発達障害の子どもが迷子になりやすい理由と対策
- ものをなくすのは発達障害の特性?理由と対策を紹介
- 発達障害で怒りをコントロールできない子どもへの対応
- 友達づきあいが苦手な発達障害の子ども。
その理由と対応法 - 発達障害児は運動が苦手?
特性とケアの方法について