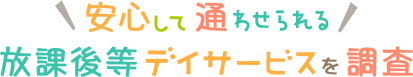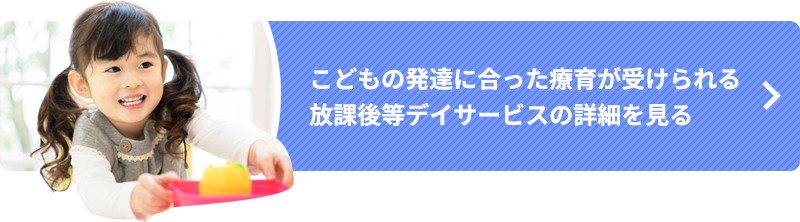発達障害と癇癪(かんしゃく)との関係とは
癇癪(かんしゃく)とはどんな状態なのか、また原因や背景に加えて対応方法についてもまとめています。
かんしゃくとはどんな状態?
まず「癇癪(かんしゃく)」とはどのような状態なのかという点について知っておきましょう。例えば下記のような行動が挙げられます。
- 泣き叫ぶ
- 手足をバタバタさせながら暴れる
- ものを投げる
- 人にあたる など
このように、暴れたり大声で泣き叫んだりするなど、興奮を伴う行動を起こすことを癇癪(かんしゃく)と呼んでいます。ただし、かんしゃくの状態はそれぞれの子どもによって異なると考えておきましょう。
かんしゃくがおきるのはどんなとき?
ここでは、かんしゃくはどのような時に起きるのかという点についてご紹介します。
何か欲求を伝えたいとき
かんしゃくの背景には、欲求不満や疲れ、空腹などがあると考えられており、「何かを伝えたいのに伝え方がわからないとき」にかんしゃくという形で現れてくる、といわれています。
成長するにつれ言葉を覚えてくると、だんだんとかんしゃく以外の言葉で伝えられるようになる場合もありますが、言葉で伝えることが苦手な場合や、かんしゃくを起こした時に「いいことが起こった」と認識すると、繰り返し同じような行動を起こす場合があります。
注目・欲求・拒否などの気持ちがあるとき
かんしゃくを起こす背景には、保護者にかまってほしい、何かがほしい、これはしたくないといった「注目されたい」「要求」「拒否」といった気持ちがあるとされています。
かんしゃくには、子どもの生活や環境などにさまざまな要因が関係しています。成長過程で起こるものであり、まったくかんしゃくを起こさない子どもの方が少ないでしょう。そのため、かんしゃくが起きるからといって子育ての方法が悪いというわけではなく、その背景を見ながら対応していくことが大切です。
また、発達障害の特性によりかんしゃくが起こりやすくなることもあるとされています。ただし、発達障害の特性があるからといって必ずしもかんしゃくを起こすわけではないため、一つの傾向として覚えておくと良いでしょう。
かんしゃくをおこさないためのアプローチ
子どもがかんしゃくを起こさなくても済むようにするにはどうしたらいいか、というサポートについて紹介します。ただし、原因は人それぞれ異なるため、興味関心や発達の段階に応じて調整することも必要です。
子どもに合った方法で見通しを立てる
例えば、楽しんで遊んでいる時間を中断させられたり、何かを強要されたと感じる時に感情が高ぶることがあります。そのため事前に「遊ぶのはこの時間まで」と見通しを立てることによって心に余裕ができ、かんしゃくを起こしにくくなる場合があるとされています。
この場合、時計のイラストを使ったりスマートフォンのタイマー機能を使うなど、子どもに合った方法を探してみることもポイントです。
気持ちを切り替える方法を決める
気持ちが高ぶった時の切り替え方法を決めておくのも良いでしょう。方法としては、「深呼吸をする」「廊下に出てひとりになる」などさまざまな方法が考えられます。何かあったときにも、この方法で気持ちを切り替えられた時にはその場で誉めるようにすると、かんしゃくを起こさなかったことでいいことがあった、と子ども自身が認識できます。
かんしゃくをおこしたときの対処法
対策をしていても、どうしてもかんしゃくが起こってしまうことはあります。ここでは、かんしゃくを起こした場合の対応方法をご紹介します。
安全を確保し、落ち着くのを待つ
かんしゃくを起こした場合には、まず子どもの安全を確保するようにしましょう。硬いものは遠ざけるなどして、ケガをしないように対策をします。安全が確保できたら、干渉せずに興奮がだんだんとおさまっていくのを待ちます。もしお店にいる場合などは外に連れ出して落ち着くのを待つと良いでしょう。
落ち着いた後にほめるようにする
子どもの様子が落ち着いたら、その場で「ひとりで落ち着けたね」といったように、どのようなところが良かったのかを含めて誉めるようにします。かんしゃくを起こしたときに感情的に叱るなどすると、逆にエスカレートする可能性もありますので、保護者の方も落ち着いて対処することが大切です。
このサイトでは、お子さまの発達具合がわかるWISC検査について解説しています。その結果を療育に活かしているおすすめの放課後等デイサービスも紹介しています。
お子さまの発達にあった療育を受けさせたいと思っている方は、ぜひ参考にしてください。
お子さまの発達がわかるWISC検査と
結果を活かす放課後等デイサービスをみる
子どもの特性が分かる発達テスト、WISC検査について解説
 お子さんの受けられる発達検査のひとつにWISC検査があります。その子の持つ特性や発達の凹凸など詳しく数値として分かるのでおすすめです。5歳~16歳11か月の検査では、「言語理解」「知覚推理」「作業記憶」「処理速度」の4項目を調べます。結果をもとに指導に反映してくれる放課後等デイサービスもありますよ。さらに詳しく検査についてまとめたページがありますのでぜひご覧ください。
お子さんの受けられる発達検査のひとつにWISC検査があります。その子の持つ特性や発達の凹凸など詳しく数値として分かるのでおすすめです。5歳~16歳11か月の検査では、「言語理解」「知覚推理」「作業記憶」「処理速度」の4項目を調べます。結果をもとに指導に反映してくれる放課後等デイサービスもありますよ。さらに詳しく検査についてまとめたページがありますのでぜひご覧ください。
- 発達障がいの子どもに通わせたい放課後等デイサービス施設
- あすなろクラブ矢作
- わくわくセブン
- ルアナランド
- Olinace八千代
- 放課後等デイサービス HERO
- 放課後等デイサービス 笑顔(ニコニコ)
- 放課後等デイサービス ぽの
- はばたき
- アースウェル
- 放課後等デイサービス そら
- 放課後等デイサービス まつどっ子
- ウィズ・ユー
- 運動療育こどもプラス新松戸教室
- 放課後等デイサービス みらい
- 放課後等デイサービス ありす
- わくわくクラブ
- LITALICO(りたりこ)
- STEP
- こぱんはうすさくら
- スマートキッズ
- ハッピーテラス
- わいわいプラス
- すきっぷ
- キッズフロンティア
- BRIDGE(ブリッジ)
- ノビルキッズ
- サンタクロース・Jr・もみの木
- かがやきのまち
- 放課後等デイサービス 学び舎
- わくわくbloom
- にじ(AIAI PLUS今井)
- アフタースクールセンター・ウェル
- わくわくぎふと鎌取
- 放課後等デイサービスまりも
- わくわくすまいる
- スマイルファクトリー
- ハビープラス
- 輝HIKARIさいたま
- ドリームボックス
- 放課後等デイサービス夢門塾
- 運動学習支援教室うめっこ本庄
- はつらつ入間教室
- はなまるキッズ
- Gripキッズ
- にこにこクラブ
- こすもすカレッジ
- 放課後等デイサービスとは?基礎知識を紹介
- 中高校生向けの放課後等デイサービスでは
どんな内容が受けられる? - 放課後等デイサービスのイベントについて
- 放課後等デイサービスの2類型化とは?
- 放課後等デイサービスにおける連絡帳の役割とは?
- 放課後等デイサービスを掛け持ちしてもいい?
- 放課後等デイサービスはいつまで通わせるとよいのか?
- 不登校の子どもは放課後等デイサービスを利用できる?
- 放課後等デイサービスの集団療育と個別療育はどちらを選ぶべき?
- 放課後等デイサービスの運動療育とは
- 放課後等デイサービスと学童の違いについて
- 放課後等デイサービスの活動内容について
- 対象となるお子さん
- 利用方法
- 受給者証の取得方法
- 料金
- 選び方
- 送迎
- 放課後等デイサービスの一日の流れ
- 事業所を変更する際の変更届について
- 発達障がいの知能検査
- 発達障害の子どもを持つ方の子育ての悩み
- 発達障がいを持つ中学生の困りごととは?
- 発達障害と癇癪(かんしゃく)との関係とは
- 発達障害の子どもの偏食・好き嫌いとその対策
- 発達障害児のお子さんの片付けをサポートするには?
- 着替えが苦手な発達障害児のサポート
- 発達障害のお子さんのお風呂の入れ方
- 発達障害のお子さんへの叱り方は?接し方で反応は変わる!
- 発達障害の我が子が勉強しない理由は?障害に合わせた対策
- 子どもが寝ないのはなぜ?発達障害と睡眠障害の関係について
- 発達障害で落ち着きのない子どもへの対応
- 言うことを聞かない発達障害の子どもへの伝え方は?
- 発達障害の子どもは感覚刺激への偏りが生じる
- 発達障害の子どもが迷子になりやすい理由と対策
- ものをなくすのは発達障害の特性?理由と対策を紹介
- 発達障害で怒りをコントロールできない子どもへの対応
- 友達づきあいが苦手な発達障害の子ども。
その理由と対応法 - 発達障害児は運動が苦手?
特性とケアの方法について