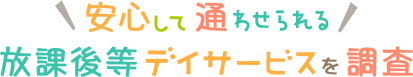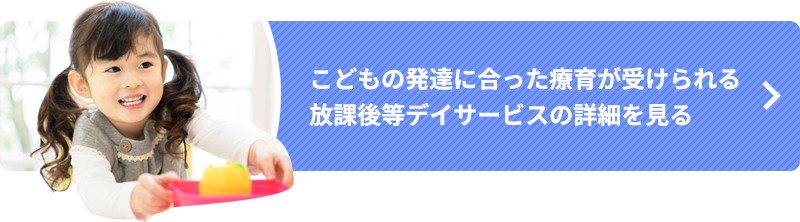友達づきあいが苦手な発達障害の子ども。
その理由と対応法
友達の輪の中にいても一人浮いてしまっている…。
大勢の中にいると必ずと言っていいほど、相手を怒らせてしまう…。
こんな状況でうちの子は友達ができるのだろうか?とお悩みのお母さんも多いのではないでしょうか。
この記事では、発達障害をお持ちのお子さんがなぜ友達ができづらいのか、また友達づきあいができるようになるために、お家でできる対応法についてご紹介します。
発達障害の子どもの特性と友達づきあいが苦手な理由
まずは、発達障害の子どもに見られがちな行動や思考の特性と友達づきあいが苦手な理由からみていきましょう。
発達障害の子どもの特性とは?
発達障害のなかでも自閉スペクトラム症(ASD)のお子さんには、以下の2つの特徴があります。
- 他人との関わり方やコミュニケーションが独特
- 特定のものごとやルールに強いこだわりを持つ
1つ目の他人との関わり方が特徴的な理由の一つとして、他人に対する関心が弱いということがあげられます。また、空気を読んで対応するといった相手の気持ちや状況を理解することを苦手としています。
2つ目の強いこだわりの背景には、自分が関心を持っていること、自分のやり方やペースを維持することを最優先したいという気持ちが見られます。こだわりが強いメリットとして、一定の分野では高い能力を発揮することができるのですが、それ以外の分野は苦手になりがちです。
発達障害の子どもが友達づきあいが苦手な理由
発達障害の子どもは、前述した特性があるため、友達づきあいにおいて非常にわがままなイメージを持たれがちです。しかし、本当はわがままなのではありません。好きなことしか集中力がない「多動性」や、思い付きですぐに行動に移す「衝動性」などが前面に出てしまい、それを自分でうまくコントロールできないことで引き起こされるイメージに過ぎません。
そのため、以下のような行動をとってしまうので、友達づきあいがギクシャクしてしまうのです。
- 順番を決めても遊具の順番を守れない
- 話し合って決めたことでも、やりたくないことはやらない
- 会話に割り込む
- ゲームのルールに関係なく、自分のやり方をつらぬく
発達障害の子どもにおすすめの友達づきあいの練習法
上記でご紹介した発達障害の子どもの特性は、その子の個性の一つです。
そこで、その個性を否定するのではなく、生きやすくするための友達づきあいを練習していくことが大切です。
友達の輪の中にいれば、やがて友達ができるか?といえば、必ずしもそうでないお子さんもいるでしょう。そこで、お母さんと1対1で友達づきあいの練習をするのがおすすめです。その際のポイントは2つです。
- ペースは完全に子どもに任せる
- 成功体験を積んでもらう
自宅でお子さんと遊びを通じて友達づきあいを学ぶだけではなく、放課後等デイサービスを利用し、じっくりと友達との関係を構築するのも大切です。できるだけ楽しく友達づきあいの練習をすることが大切なので、トランプやだるまさんがころんだなどのゲームがおすすめ。
たとえば、お子さんがルールを守っていない時は「あれ?ルールはどうだったかな?」と考えさせ、ルールを守れた時は「そうそう、順番守れたね。○○くんの次はお母さんの番だよね」と声をかけてあげたりするといいでしょう。
こうすることで、順番やルールを守りながら楽しむことが少しずつできるようになるでしょう。特性を変えることはお子さんとしても難しいものです。焦らず根気強く楽しみながら行うのがポイントです。
まとめ
発達障害の子どもは、他者との関わりが苦手で、こだわりが強い特性があることから、友達づきあいに悩んでしまうことも多いものです。 自宅でお子さんと遊びを通じて友達づきあいを学ぶだけではなく、放課後等デイサービスを利用し、じっくりと友達との関係を構築し友達づきあいに関する経験を積むこともおすすめです。友達ができてくれば、放課後等デイサービスがお子さんにとって第二・第三の居場所にもなっていくでしょう。
このサイトでは、お子さまの発達具合がわかるWISC検査について解説しています。その結果を療育に活かしているおすすめの放課後等デイサービスも紹介しています。
お子さまの発達にあった療育を受けさせたいと思っている方は、ぜひ参考にしてください。
お子さまの発達がわかるWISC検査と
結果を活かす放課後等デイサービスをみる
子どもの特性が分かる発達テスト、WISC検査について解説
 お子さんの受けられる発達検査のひとつにWISC検査があります。その子の持つ特性や発達の凹凸など詳しく数値として分かるのでおすすめです。5歳~16歳11か月の検査では、「言語理解」「知覚推理」「作業記憶」「処理速度」の4項目を調べます。結果をもとに指導に反映してくれる放課後等デイサービスもありますよ。さらに詳しく検査についてまとめたページがありますのでぜひご覧ください。
お子さんの受けられる発達検査のひとつにWISC検査があります。その子の持つ特性や発達の凹凸など詳しく数値として分かるのでおすすめです。5歳~16歳11か月の検査では、「言語理解」「知覚推理」「作業記憶」「処理速度」の4項目を調べます。結果をもとに指導に反映してくれる放課後等デイサービスもありますよ。さらに詳しく検査についてまとめたページがありますのでぜひご覧ください。
- 発達障がいの子どもに通わせたい放課後等デイサービス施設
- あすなろクラブ矢作
- わくわくセブン
- ルアナランド
- Olinace八千代
- 放課後等デイサービス HERO
- 放課後等デイサービス 笑顔(ニコニコ)
- 放課後等デイサービス ぽの
- はばたき
- アースウェル
- 放課後等デイサービス そら
- 放課後等デイサービス まつどっ子
- ウィズ・ユー
- 運動療育こどもプラス新松戸教室
- 放課後等デイサービス みらい
- 放課後等デイサービス ありす
- わくわくクラブ
- LITALICO(りたりこ)
- STEP
- こぱんはうすさくら
- スマートキッズ
- ハッピーテラス
- わいわいプラス
- すきっぷ
- キッズフロンティア
- BRIDGE(ブリッジ)
- ノビルキッズ
- サンタクロース・Jr・もみの木
- かがやきのまち
- 放課後等デイサービス 学び舎
- わくわくbloom
- にじ(AIAI PLUS今井)
- アフタースクールセンター・ウェル
- わくわくぎふと鎌取
- 放課後等デイサービスまりも
- わくわくすまいる
- スマイルファクトリー
- ハビープラス
- 輝HIKARIさいたま
- ドリームボックス
- 放課後等デイサービス夢門塾
- 運動学習支援教室うめっこ本庄
- はつらつ入間教室
- はなまるキッズ
- Gripキッズ
- にこにこクラブ
- こすもすカレッジ
- 放課後等デイサービスとは?基礎知識を紹介
- 中高校生向けの放課後等デイサービスでは
どんな内容が受けられる? - 放課後等デイサービスのイベントについて
- 放課後等デイサービスの2類型化とは?
- 放課後等デイサービスにおける連絡帳の役割とは?
- 放課後等デイサービスを掛け持ちしてもいい?
- 放課後等デイサービスはいつまで通わせるとよいのか?
- 不登校の子どもは放課後等デイサービスを利用できる?
- 放課後等デイサービスの集団療育と個別療育はどちらを選ぶべき?
- 放課後等デイサービスの運動療育とは
- 放課後等デイサービスと学童の違いについて
- 放課後等デイサービスの活動内容について
- 対象となるお子さん
- 利用方法
- 受給者証の取得方法
- 料金
- 選び方
- 送迎
- 放課後等デイサービスの一日の流れ
- 事業所を変更する際の変更届について
- 発達障がいの知能検査
- 発達障害の子どもを持つ方の子育ての悩み
- 発達障がいを持つ中学生の困りごととは?
- 発達障害と癇癪(かんしゃく)との関係とは
- 発達障害の子どもの偏食・好き嫌いとその対策
- 発達障害児のお子さんの片付けをサポートするには?
- 着替えが苦手な発達障害児のサポート
- 発達障害のお子さんのお風呂の入れ方
- 発達障害のお子さんへの叱り方は?接し方で反応は変わる!
- 発達障害の我が子が勉強しない理由は?障害に合わせた対策
- 子どもが寝ないのはなぜ?発達障害と睡眠障害の関係について
- 発達障害で落ち着きのない子どもへの対応
- 言うことを聞かない発達障害の子どもへの伝え方は?
- 発達障害の子どもは感覚刺激への偏りが生じる
- 発達障害の子どもが迷子になりやすい理由と対策
- ものをなくすのは発達障害の特性?理由と対策を紹介
- 発達障害で怒りをコントロールできない子どもへの対応
- 友達づきあいが苦手な発達障害の子ども。
その理由と対応法 - 発達障害児は運動が苦手?
特性とケアの方法について